育休に入って1ヶ月目は、目の前の育児に精一杯で、とにかく“やれることをやる”毎日でした。 オムツ替え、ミルクの準備、抱っこで寝かしつけ…。 やっているつもりではあったけれど、正直なところ、それは“妻を助ける”というより、“育児の一部を手伝っている”感覚に近かったのかもしれません。
しかし2ヶ月目に入ると、少し変化がありました。
育児の流れが少しだけ読めるようになり、赤ちゃんの泣き声にも“なんとなくの種類”が分かるようになってきたのです。
そんな中でふと気づきました——「妻の支え方って、もっと進化させられるんじゃないか」と。
1. 手伝うではなく、先回りする
1ヶ月目は「何かやることある?」と聞くことが多かった僕。
でも、この質問は、妻に“考えるタスク”を増やしてしまうこともあります。
2ヶ月目からは、妻の動きや表情から必要そうなことを先回りしてやるようにしました。
哺乳瓶を洗っておく、洗濯物を取り込む、授乳後の赤ちゃんを受け取って寝かしつけに入る——言葉にする前に動くことで、妻が少しだけ横になる時間が増えました。
2. “ありがとう”を言葉で伝える
毎日一緒にいると、感謝の言葉は意外と減ってしまいます。 でも、深夜の授乳や寝かしつけを何度もこなす妻の姿を見るたびに、「これを当たり前に思っちゃいけない」と思いました。 そこで意識して、どんな小さなことでも「ありがとう」と声に出すようにしました。 不思議なもので、ありがとうを言うと、自分自身の気持ちも柔らかくなります。
3. 妻の“ひとり時間”を守る
育児は2人でしていても、どうしても母親の負担が偏りがちです。
2ヶ月目からは「今日は僕が見るから、30分だけ外に行っておいで」と提案するようにしました。
たった30分でも、カフェでコーヒーを飲む、静かに本を読む、それだけで妻は少し表情が明るくなります。
僕にとっても、赤ちゃんと二人きりで過ごす時間は新しい発見の連続でした。
4. “僕から”話を聞く
育児中は、会話も業務連絡のようになりがちです。 だからこそ、寝かしつけ後に「今日はどうだった?」と僕から聞く時間を持つようにしました。 愚痴でも、嬉しかったことでも、ただ話すだけで気持ちは軽くなる。 そして妻の言葉の中に、「次はこうした方がいいかも」というヒントがたくさん隠れていました。
5. 自分の疲れも正直に話す
支えるつもりで無理をしすぎると、こちらも心がすり減ります。 だからこそ「今日は少し疲れてるかも」と正直に伝えることも大切だと感じました。 弱さを見せ合えると、お互いが“助け合う側”にも“支えられる側”にもなれる。 この関係こそが、長く続く育児の土台になると思います。
育休2ヶ月目、僕は「支える」という言葉の意味を少しだけアップデートできた気がします。 それは、特別なスキルや体力が必要なことではなく、“相手をよく見て、小さな行動を積み重ねること”。 そして何より、その変化は赤ちゃんにも伝わっているのか、妻の笑顔が増えると、不思議と赤ちゃんもよく笑うようになった気がするのです。
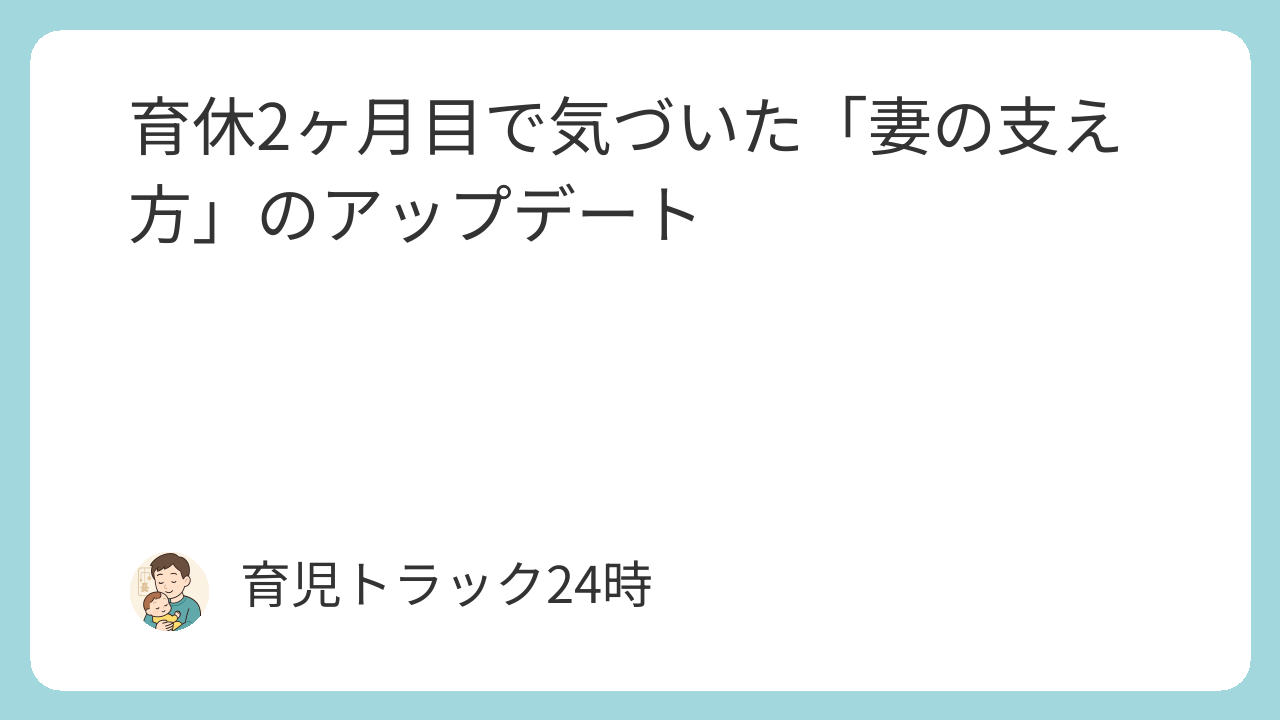

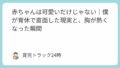
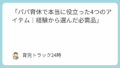
コメント